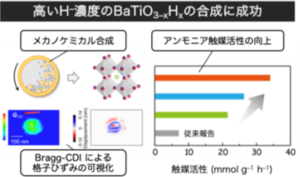茨城大学大学院人文社会科学研究科に2025年4月、「ダイバーシティ地域共創教育プログラム」が開設されました。ダイバーシティ経営や持続可能な地域経済の発展に貢献する人材の育成をめざすもので、茨城大学・宇都宮大学・常磐大学の3大学の連携で運営します。
概論の授業が終わり、6月にはさまざまな分野で活躍する外部講師を招く授業「ダイバーシティ地域共創最前線」がスタートしました。
この授業では、ジェンダー、子ども、多文化共生、メディア、まちづくりなどの分野の最前線で活動する講師の皆さんが、実践の現場で重視していることや感じている課題を話します。
6月25日の授業では、連携大学でもある宇都宮大学から、石井大一朗教授(地域デザイン科学部)が登壇。長年まちづくり・地域づくりの実践に取り組む石井教授は、「協働と共創」をテーマに講義しました。

石井教授は、ジェンダーギャップ指数(GGI)を用いて、日本は教育や健康の分野では世界トップクラスの一方、政治参画がほぼ0(0.085)であることを紹介。地方自治体の管理職の男女比なども示しつつ、自治会長の女性割合はさらに減少するとし「より身近なところでの意思決定は極めて女性が少ない」と問題点を指摘。「同じような属性の人間だけになった組織は、早い段階で停滞していく。異なりを恐れず、異なるセクター同士の生かし合い・支え合いが大切」と話しました。
また、自治体の市民協働指針を分析した結果を示し、「協働には原則がある」と話します。多くの自治体に共通するのは①対等②相互理解③目的共有・相互評価④自主性・自立化⑤公開―の5点。特に対等について、「異なる組織が協働で何かをする場合、支配する/されるの関係が必ず生まれる。それをどう乗り越えていくか」「対等であるからこそ新しい発見ができ、互いの力を最大限にできる。力の総和を最大にするには対等でなければいけない」と主張しました。
最後に、自身が栃木県・真岡市で取り組むまちづくり事業について紹介。有志の大人と地元の高校生とのかかわりを軸に、事業ごとに中学生や障害者作業所、地域商店街など異なる組織と連携しており、はじめは河川敷にて1日限定で始めたドッグランが常設になるなど、周囲を巻き込みながら市民主体で暮らしやすいまちをつくっているといいます。
高校時代に関わった人が、進学後に戻ってきてまたプロジェクトに参画してくれる事例もあり、「こうした人の循環はまちづくりのゴールの一つ。とてもうれしいことです」。
こつは「小さくできることをさっとやっちゃう『スモールスタート、クイックスタート』」。「異なる組織、コミュニティが対話をし、スモール&クイックスタートで何かを生み出していく一連の営みによって、ダイバーシティはつくれます。3年あれば実現します」と総括しました。
同プログラムでは今後、連携する企業や自治体、NPOに赴き、実践的な演習も行う予定。