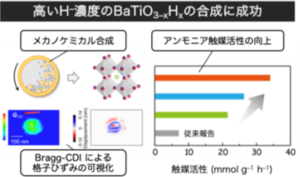教育学部は2025年度から、1年生が全員受講する「大学入門ゼミ」内で、救命講習を行うことを決めました。教職を目指す学生たちが、将来、学校や地域でためらわず救命処置への対応ができるようにするのが目的。一般社団法人水戸地区救急普及協会の協力で、e-learningと実技で基本的な知識と技術を身に付け、学生一人ひとりには水戸市消防局から「普通救命講習I修了証」のカードが発行されました。
教員が児童生徒等の命を守るため、AED(自動体外式除細動器)の使用や心肺蘇生等の応急措置を迅速に、適切に行えるようになることは、安心・安全な学校運営のために重要です。しかし、教材準備や外部講師手配などの難しさから、教員養成で必修としている授業内で一次救命処置に関する講義・実習を行っている大学は3割、AEDを用いた実習を行っている大学は1割程度にとどまっています。
そんな中、茨大教育学部は、これまで4年生全員(一部の課程を除く)と、3年生の一部の課程・コースで、一次救命処置に関する講義・実習、AEDを用いた実習に取り組んできました。
さらに今年度から、救命への意識を高めることを目的に、入学後の早い段階から全員が一次救命処置の基礎を学ぶこととしました。
この「普通救命講習I」は各課程やコース、選修ごとに30人程度に分かれて行いました。4月23日からほぼ毎週行われ、7月9日、音楽選修、英語選修への講習で最後です。
講習ではまず、テキストを基に、意識の有無の確認の仕方や、胸骨圧迫、人工呼吸の方法、AEDの使用方法などをおさらい。続いて、4人ほどのグループに分かれ、人形を用いて実践しました。
グループ内で交換しながら、1人当たり150回ほど胸骨圧迫の実技を行いました。指導員の指示を聞きながら、学生たちは真剣に取り組みます。実技が終わると拍手が生まれ、指導員の方とハイタッチする学生の姿がありました。
講習を終え、学校教育教員養成課程教科教育コース英語選修の佐藤怜さんは「言葉だけで説明を受けてもイメージしにくいが、実技を行うことで実際の現場をイメージすることができた。応急処置が必要な場に居合わせたら、緊張すると思うが、冷静に、周りと協力しながら対処できると思う」と自信を付けた様子。
学生とともに講習を受けた安原正貴准教授は「覚えられたと思っても、少し経つと忘れていることもある」と学び続ける大切さを指摘します。保健体育・養護教諭を目指す学生だけでなく、全員が学ぶ意義を「人任せが避けられる。誰の前でも起きることなので、子どもを預かる教員は身に付けておくべき」と話しました。
(取材・構成:茨城大学広報・アウトリーチ支援室)