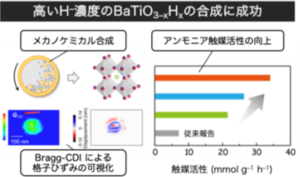「聞こえづらさ」による疲労の影響や聴覚のケアについて考えるセミナー「ライブ版『みんなで創るきこえのミライ』」が、6月22日、JR大阪駅近くのホールで開催され、約80人の方が参加しました。茨城大学教育学部の田原敬准教授の研究室と、岡山大学病院聴覚支援センター、オーティコン補聴器の共同主催によるもので、田原准教授らとともに補聴器ユーザーの方も登壇しました。
リスニング・エフォートとリスニング・ファティーグ
加齢に伴う難聴や若年性のイヤホン難聴などによる「聞こえづらさ」があると、集中を高めて聞き取ろうとしたり、聞き取れなかった内容を推測したりして、聴覚以外の認知機能も総動員して理解しようとします。これを「リスニング・エフォート(聞き取り努力、LE)」と呼び、そのことによって引き起こされる疲労感は「リスニング・ファティーグ(聞き取りによる疲れ、LF)」と呼ばれます。
田原准教授は、聴覚障害の研究がさかんなデンマークなどで深く学んだLE・LFについて、特に子どもたちの検査やケアの研究を進めています。あわせて全国で啓発活動にも取り組んでおり、今回のセミナーもその一環で企画に参加しました。
技術や仕組みを使いこなした多様な対応を

セミナーではまず、岡山大学病院聴覚支援センターのセンター長補佐で医師の片岡祐子准教授が、「医療・技術・社会で創るきこえのミライ」と題して講演を行いました。
片岡准教授は、雑音の中で声を区別する・必要な成分を抽出する・文脈を通じて足りない音を補強する―といった聞き取りから、音韻処理・意味処理という理解に至る、複雑なプロセスを解説しました。
その上で子どものLE・LFにおいては、補聴や支援、配慮が不十分な場合、理解の困難さや学力低下、自身の喪失などにつながることもあると述べ、通常学校でできる配慮として、「どんな聞こえかを理解してはっきりゆっくりテンポを崩さずに話す」「静かな環境で話をする」「雑音のない状況で話しかける」「視覚情報を使う」などを挙げました。
一方、最近は補聴器にもAIが搭載されており、また教育のデジタルコンテンツも多様化していることから、「『聞き取り』だけがすべてではありません。オンライン相談や生成AI、メタバースでの情報、当事者コミュニティといった高度な技術や仕組みを人や社会が使いこなせるようになり、個々の長所を活かす社会、活躍・貢献できる社会がなっていくことが大事だと思います」と語りました。
「疲れ」と「自分の得られたもの」のバランス
対応や捉え方の多様化という点では、次に登壇した田原准教授も、「リスニング・エフォートが高いということが本当に悪いことなのか、ということも考えてみたい」と話しました。
ガヤガヤした環境で話を聞こうとするとき、頑張ってでも聞きたいと思うか、面倒くさいから聞かなくてもいいと思うかは、モチベーションによって変わってきます。すなわち、エフォートが高いということは、その話が聞きたいということなんです。田原准教授は、「エフォートの高さによって自分の人生や生活に影響が出ないようにすることを考えるのが大事」としたうえで、「疲れは出るけれど自分はこんな満足感がある、という考えが重要。疲れと自分の得られたもののバランス、一人一人が自分の意志や価値をもって判断することが求められてきていると思います」と指摘しました。

LE・LFの大変さを周りの人たちに知ってもらうこと
続いて登壇したのは、幼少時より補聴器を装用、先天性の感音性難聴があり、普通学級での学びを経て現在は大手のIT企業に勤める井上晶雄さんです。
井上さんは、脳をフル稼働させ、通常の何倍もの認知的負荷をかけながら「聞く」ことの大変さを、かつては周りの人に言えなかったと話します。その理由として、①周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか、②理解されないのではないかと言う不安、③がんばればどうにかなるという努力・思い込み、④特別扱いを受けてしまうことへの心理的負担―を挙げました。
しかし、周りに伝えられないことにより、疲労の蓄積や仕事のパフォーマンスへの影響、ひいては積極的に人と話そうとしないことによる人間関係への影響や社会参加意欲の減退といったことが起こっていきます。井上さんは「(努力や疲れについて)黙っていることは双方にとってよくない」と感じるようになり、自分から周りに配慮を求めるようになったと言います。具体的には、右か左かといった話す位置や、違う言葉で言い換えてもらうなどの話し方、声の大きさというより明瞭さなどのポイントを伝えるようにしました。
井上さんは、「人によって最適な環境は違う。自分の特性を理解した上で、疲れたときは休息をとるのも大事」「周りからはなかなかわからないので、自分からのアクションも大切」と呼びかけました。
評価の体験とトークセッション

後半は、田原准教授が開発しているリスニング・エフォートの評価方法を、個々に配られたワークシートと会場のオーディオを使って、参加者が体験しました。雑音とともに流れる音声を聞き取ってそれを復唱しながら、手元で計算を行うというものです。実際の調査では、こうしたテストに取り組んでもらいながら、さらに心拍数など、スマートデバイスで計測できる生体データにも注目して評価を行っています。
最後は片岡准教授、田原准教授、井上さんが並び、トークセッションを行いました。会場からは、「就労時間内で疲れを軽減する工夫は?」「周囲に配慮を求められるようになったきっかけは?」といった当事者の視点からの質問などが届き、3人がそれぞれの立場で回答していました。
また、「普段補聴器をつけていることを恥ずかしがる子どもにどういうアドバイスをしていますか」という質問に対しては、医師でもある片岡准教授が、「『恥ずかしくないよ』というのも難しいと思う。恥ずかしいという気持ちも事実。聞こえにくいのを補聴するのは当たり前のことですが、本人の気持ちも汲み取りながら、『それでも楽に聞けたらいいね』という気持ちで対応しています」と答えました。

田原准教授、片岡准教授、オーティコン補聴器の共同主催による「みんなで創るきこえのミライ」では、動画コンテンツもこれまで2シリーズを配信してきました。第3弾も近日配信予定です。