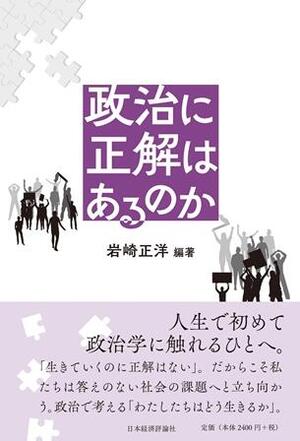「フェミニスト経済学」という言葉、聞いたことがありますか? 茨城大学人文社会科学部の長田華子准教授が共編著を務めた『フェミニスト経済学』(有斐閣,2023)では、フェミニズムの視点から経済学をとらえる学問であり、主流派の経済学とは別の、異端派の経済学の一つだと説明されています。7月26日(土)、水戸キャンパスで日本フェミニスト経済学会2025年度大会が開催されます。その座長も務める長田准教授にインタビューをしました。
―『フェミニスト経済学』の発刊から2年近くが経ちます。反響は?
長田「フェミニスト経済学とは何か、フェミニスト経済学が対象とする領域や研究課題を日本語で学べる初めてのテキストということで、予想以上の反響の大きさです。私たちが読者として想定していた学生や大学教員、研究者だけでなく、一般の読者の方にも沢山読んでいただいていることに驚いています。『経済学をジェンダーの視点を取り入れてみると、こんなにも見える世界が広がるのか』や『ケア労働の賃金の低さに対するモヤモヤが解消された』といった声をいただいています。週刊ダイヤモンド2024年『ベスト経済書』の9位にランクインしたことは、私たち執筆者にとって大きな喜びでした。それだけ、いまの世の中において、フェミニスト経済学の考え方が必要されているのだとも感じています」
―米国のトランプ政権はDEI(多様性・平等・包摂)の諸活動を敵視しています。日本では、ジェンダー格差、不平等が一向に解消されない中で、フェミニスト経済学に求められる役割は大きいのでは?
長田「一国の大統領(しかも、世界第1位の経済大国のアメリカの大統領)が、公然と、ジェンダーやフェミニズムを否定するような発言をし、それが、政治の道具として使われるのは本当に恐ろしく、決して容認できることではないと思います。日本でも毎日のようにトランプ大統領の言動がメディアで報じられる中で、反DEI的な言説がじわじわと広がっていると感じ、懸念しています。日本では、相変わらずジェンダー格差、不平等が大きいにもかかわらず、社会の中でDEIの活動を後退させるようなことがあってはならないと思います。多様性、包摂性を重視することは、すべての人々の人権を保障し、すべての人々がよりよく生きる上でとても重要なことなのです。フェミニスト経済学は、経済的な成功としてすべての人々のウェルビーイングの向上を目的としています」
―今後の日本での「フェミニスト経済学」の広がりについては?
長田「『フェミニスト』と『経済学』という言葉から連想されるものが、日本と諸外国では異なるように思います。欧米の主要な経済学会では、『フェミニスト経済学』が主流の経済学とは異なる、異端派の経済学の一つとして位置づけられているのに対し、日本ではそうした捉え方が十分に根付いているとは言えません。フェミニスト経済学の国際的な学会として、国際フェミニスト経済学会(International Association for Feminist Economics: IAFFE) が1992年に設立され、毎年世界中で、大会を開催していますが(今年はアメリカのボストンで開催されました)、欧米でも、新興国でも、男性の研究者の参加も多いです。その他、研究者のみならず、国連やNGO、行政分野の実務家など、研究者以外の参加が多いのも、日本とは少し異なる特徴だと思います。フェミニスト経済学は、ジェンダーのみならず国籍、民族、宗教、年齢や障害の有無、社会的身分などを分析の視角に加え、経済社会状況を読み解きます。不可視化されていた問題を可視化して、どのようにしたらすべての人のウェルビーイングを向上させることができるかを考える、そんなフェミニスト経済学は今こそ必要とされていると思います。日本におけるフェミニスト経済学のプレゼンスをもっと高められないかと、今、日本国内で国際フェミニスト経済学会の大会を招致するために活動しています。7月26日の大会のプログラムの11時半~12時のIAFFEトークセッションでは、今年のボストンでの大会に参加した学会員が大会の様子を報告します」
―フェミニスト経済学の知見を国や自治体の政策に活かす手立ては?
長田「ジェンダー統計やジェンダー予算などが挙げられます。ジェンダー予算は、ジェンダー主流化のためのツールとしてとても重要です。ジェンダー予算と聞くと、女性を対象とした事業(例えば、乳がん検診や周産期医療体制整備事業など)に予算を付けることを想定するかもしれませんが、それだけではありません。テキストにも記したように、ジェンダー予算とは、インフラ整備や環境、産業振興などのような一見ジェンダーとは関係のないようにみえる予算も対象とし、それらが、ジェンダー平等を促進しているのか、後退させているのか、あるいは変化がないのかを分析し、その結果を予算や政策立案に、活用する手法です。実際に政策に生かすためには、政策策定者がジェンダー予算に関する知識や能力を身に着けていなければなりません。私が、サバティカルで滞在したイギリスでは、女性団体や研究者が、地方の女性団体を対象に、ジェンダー予算に関する能力開発のプログラムやワークショップを開催し、市民の能力向上をはかる取り組みを行っていました。国だけでなく、地方レベルで、ジェンダー予算の分析ができる市民を育てていくことは、とても重要なことだと思いました。」
―本学の大学院人文社会科学研究科では、今年4月からダイバーシティ地域共創教育プログラムが開設されました。ここで育成するのもそうした人材ですね。
長田「まさにそうです。大学院の2年間で、多様性、包摂性の重要性をしっかり学んだ方が、社会に出て、社会を変えていく。茨城大学、宇都宮大学、常磐大学の三大学が連携してプログラムを運営していますが、地方だからこそ必要な教育プログラムだと思います。ジェンダー、国籍、人種、民族などを超えて、地域に住む、すべての人が持ちうる能力を最大限発揮できる社会を作る上では、多様性や包摂性に関する専門的な知識を学んで、自ら行動できる人が必要です」

―7/26に行われる日本フェミニスト経済学会2025年度大会では、共通論題テーマとして「フェミニスト経済学と農業:『資源』化する農の担い手の現在」を掲げています。なぜ農業に着目を?
長田「せっかく茨城大学で開催するので、茨城県ならではのテーマにしたいということが念頭にありました。茨城県は、農業県であり、ぜひ『農』や『食』をテーマとしたいと考えるようになりました。昨年夏からの米の不足と米価格の高騰もあり、最近では連日のように農業の話題が報道されています。いかに、私たちの「食」が農業の営みと地続きであるかを、私自身が実感するようになったことも影響しているかもしれません。今回は特に農の『担い手』に着目しています。茨城県でも最近は、農地を集約した法人経営が増えていますが、昔ながらの家族経営で農業を営んでいる農家さんも沢山います。昔に比べて、国による農業分野における男女共同参画の施策や取り組みもあり、地域コミュニティや世帯内のジェンダー平等の状況は変わりつつあるとはいえ、まだ昔ながらの考え方や慣習が残っているところも多くあります。
また、農業の担い手が減る中で、女性に加えて、近年は外国人労働者、障害者など多様な『担い手』あるいは『人材』が注目され、動員されています。今回の「『資源』化する農の担い手」というタイトルの言葉は、市場化、資本主義化する農業において、農業の「担い手」が道具化、商品化される状況を表現するものとして用いています」
―メインの議論では、長田先生が座長を務め、5人の方が報告を行います。
長田「岩島史さんの専門はジェンダー史、農業経済学です。今回、社会的再生産の危機という観点から、戦後の農政を振り返り、農業の『担い手問題」を解消するために、女性や外国人労働者、障害者が、どのように『発見』され、動員されるにいたったかを報告いただきます。飯田悠哉さんは、長野県の高冷地のレタス栽培の農家でのフィールド調査を事例に、移民農業労働者の健康被害について、ケア秩序の変化という観点から報告いただきます。佐藤洋子さんは、これまで地方における女性の働き方に関する研究を行ってこられました。農業のみならず、林業における女性たちの仕事や活動に関しても、研究されています。今回は、佐藤さんと共同研究者が調査された4道県の農業委員への大規模調査の結果と、そこから見えてくる、農業委員の活動に見る『女性向き』の役割について、報告いただきます。私自身、今回座長を務めるにあたって、茨城県の農林水産部や水戸市農業委員事務局を訪問し、担当者に話を聞きました。消費者が安価な『食』を求めるプロセスの中で、農の『担い手』にどのようなしわ寄せが生じているのか、考えるきっかけになりました。私が専門としている、安価な洋服を求める消費者と、衣服製造の「過酷」な労働の問題と、共通点が多いようにも感じています」
―3人の研究者に加えて、地域の農業実践者も報告します。
長田「棯﨑ひろ子さんは夫婦で、水戸市内で梨農園を営まれています。茨城県では1990年に、婦人農業士制度が発足しますが、棯﨑さんは、その女性農業士の第1期生です。棯﨑さんには、これまでのご自身の農業従事者としての活動の歩みとともに、2002年に、夫婦で締結された家族経営協定の詳細についてお話ししていただく予定です。家族経営協定については、フェミニスト経済学の関心事である世帯内の意思決定に関連するテーマであり、今回棯﨑さんから、その具体的なお話を伺えるのは、私たち研究者にとっても大きな学びになると思っています。
また、姜咲知子さんは、石岡市で『暮らしの実験室やさと農場』を共同経営者の1人として、運営しています。暮らしの実験室の活動や、大切にしているコンセプトをお話ししていただく中で、市場化、資本主義化する農業とは別の、コモンとしての農業の実践について学ぶとともに、そうした活動が、地域コミュニティの維持において何をもたらしているのか、考える機会にしたいと思っています」
―誰かが必要としているものを届けるという「プロヴィジョニング』が、フェミニスト経済学の重要な概念であるとテキストに書かれています。農と食はプロヴィジョニングの最たるものといえそうですね。
長田「米価格の高騰とその後の農政の対応をみても、いかに私たち消費者が安価な農産物を求めているか、そして私たちの生活が安価な「食」に支えられているのかがよくわかります。他方で、その価格が農業従事者にとっての正当な対価、価格であるかどうかは、私たちが今一度考えなければならないことだと感じます。農業の『担い手』不足の根幹には、農業従事者の多くが正当な対価を得られず、経済的に苦労している現状があるのだと思います。農家の生産性の向上、所得の向上はもちろん大事だとは思いますが、それだけではないはずです。たとえば農業従事者が子どもの保育や親の介護に直面したときに、充分な社会的サービスにアクセスできているかどうか。当日は、私たちの『食』を支える農の『担い手』について参加者のみなさんとじっくりと考えていきたいと思っています」
―改めてフェミニスト経済学の射程の広さを感じます。
長田「これまでに登壇者で二度研究会を行い、当日に向けて準備を進めてきました。報告者のお一人である飯田さんから、農業は動植物と農業労働者という2つをケアする営みであるとお聞きしたときには、目から鱗でした。気候変動が進む中で、動植物のケアと農業労働者のケアとの両立をどう考えるか。フェミニスト経済学の視点はどこまでも広がります」
日本フェミニスト経済学会2025年度大会
| 日時 |
2025年7月26日(土)10:00~17:45(共通論題は13:00~17:45) |
|---|---|
| 会場 |
茨城大学水戸キャンパス人文社会科学部講義棟 |
| 参加費 |
会 員(一般 1000 円、学生・非正規等 無料 ) |
| 主催 |
日本フェミニスト経済学会 |
| 協賛 |
茨城大学大学院人文社会科学研究科 |
※ 必ず申込をお願いします。詳細はこちらhttps://events.admb.ibaraki.ac.jp/2025/24001265.html