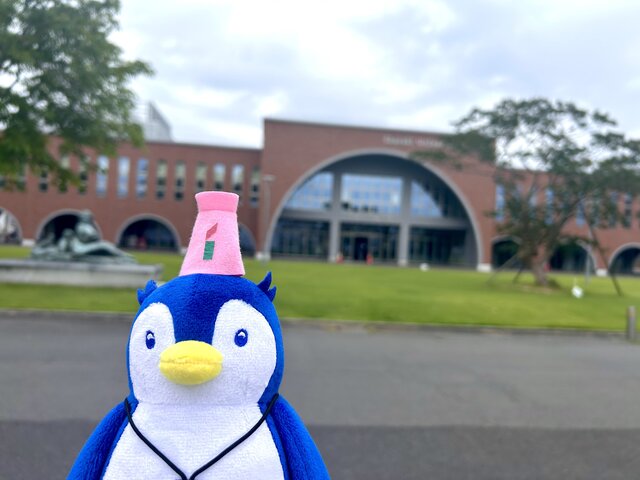災害の体験を「語る」「聞く」場をつくりたい
―大子清流高等学校で防災ワークショップ 企画した学生の想い

災害の体験をどのように記録し、地域で共有して、まちの未来へとつなげていくか―
2019年の台風災害で大きな被害を受けた茨城県北の大子町では、人文社会科学部の伊藤哲司教授らとの連携のもと、住民へのインタビューやワークショップなどを行いながら、記録集の作成を進めています。
2月21日には茨城県立大子清流高等学校で、総合学科の1年生28人が参加しての防災ワークショップが開催されました。高校生たちが町の人たちの体験談を聞いた上で、自分たちのまちがこれからどうあってほしいかを考える2時間のプログラム。中心となって企画をしたのは、卒業研究で東日本大震災の「語り部」についての調査に取り組んだ4年生の学生でした。
2019年10月の台風19号災害では、大子町においてもJR水郡線が長期間にわたって不通になるなどの大きな被害に見舞われ、大子清流高等学校の生徒たちや町外の学校へ通う高校生たちの生活にもさまざまな影響が生じました。
当時茨城大学では災害調査団を発足させ、地質や気候の面からの原因究明、避難状況、報道の分析といった多様な切り口から調査活動を行い、その過程で県内各地の被災地の方々とも連携を図ってきました。
このうち大子町では、人文社会科学部の伊藤哲司教授らが中心となり、台風19号の被災体験を聞いてこれからの大子町について考えるというプロジェクトをスタートさせました。町との協力のもとフィールドワークやワークショップなどを実施し、それらの内容を記録集にまとめる計画で、昨年(2022年)6月1日には袋田地域防災センターでも住民参加のワークショップを行いました。今回の大子清流高等学校でのワークショップもその一環で企画されたものです。
 ワークショップの教室に展示された被災当時の写真
ワークショップの教室に展示された被災当時の写真
ワークショップの前半では、まず、大子町役場の総務課職員として発災当時から対応にあたってきた皆川敦史さんが、スライドで当時の写真なども見せながら、災害の全容とその後の復旧作業の状況を説明しました。皆川さんは、「水害の跡が目に見えないぐらいにまちは戻ってきていますが、もっと災害に強いまちにするにはどうしたら良いか、若い高校生のみなさんに一緒に考えてもらいたいです」と呼びかけました。
皆川さんと同じ総務課職員の柳下月菜さんは、大子清流高校の卒業生。当時、まさに高校生でした。「台風が来たのが文化祭の1週間前だったんです。前の日はいつも通りに過ごし、いつも通り家に帰っていたのに、日が変わったら状況が一変しました」と振り返ります。2日後に学校は再開したものの、何人かの人は登校することができなかったそうです。
そうした状況でしたが、文化祭は予定どおり実施しました。「みんなが元気な気持ちになるものをつくろう」、その思いで、復興のメッセージを込めた大きな旗も作り、来場者を出迎えたそうです。
 高校生に話をする(奥から)皆川さん、柳下さん、髙瀨さん
高校生に話をする(奥から)皆川さん、柳下さん、髙瀨さん
災害体験の記録集というと、冊子状のものを思い浮かべますが、今作成を進めているのはインターネット上の地図に写真やテキストを記録していき、それをみんなで共有しながら、なおかつ常にアップデートしていく「語りマップ」というものだそう。いわば完成しない記録集。具体的にはGoogleのマイマップという機能を活用しています。その説明をした元教員で、町内の被災の様子を写真で記録してきた髙瀨一仁さんは、「この地図は誰でも見ることができるし、誰でも書き込むことができる。被災を直接体験した人だけでなく、ぜひみなさんにも、今日のワークショップを踏まえた想いなどどんどん書き込んで、一緒に作っていってほしいです」と生徒たちに語りかけます。
町の人たちの話を聞きながら、高校生たちも災害を自分ゴトとして捉えようとしていました。お父さんが水郡線の橋の復旧工事に関わったという生徒は、「父が『難しい仕事だ』と話していたのを覚えています。僕も人の役に立つ仕事をしたいので、今度こうした災害があったら積極的にボランティアに参加したいです」などと語っていました。
かわって後半はグループワークです。1グループ4人で、それぞれの机に模造紙を広げ、前半で水害についての話も踏まえて、大子町の良いところ、足りないと思うところを書き出し、話し合っていきます。
大子町の良いところとして各グループで共通して挙げられていたのが、山や川、袋田の滝などに代表される自然の豊かさや、リンゴや軍鶏(しゃも)といった特産物、さらに「人が優しい」というコミュニティの親密さです。
一方、足りないと感じる点は、高速道路が通っておらず移動に不便がある、若者が遊べる娯楽施設がない......など。
これらひとつひとつを付箋に記し、模造紙の上で整理をしながら、「じゃあどうすればいいだろうか」ということを考え、話し合っていきます。どのグループでも活発に議論が進み、まちに人を集めるアイデアやその実現に必要な考え方などをまとめ、模造紙に記していきました。
「まちのこれからについてこんなに真剣に考えたり、友達と話したりしたことはありませんでした」などと感想を語った高校生のみなさん。チャイムが鳴った後も多くの人が教室に残り、議論の余韻に浸っている様子でした。
さて、今回のワークショップの企画・運営において中心的な役割を果たしたのが、伊藤教授のゼミに所属する4年生の佐藤美理さんです。
佐藤さんは秋田県出身。2011年の東日本大震災のときは小学4年生でした。日本海側の秋田はそこまで大きな被害はなかったそうですが、同じ東北地方を襲った未曾有の災害に衝撃を受け、自分でも何か役に立つことをしたいという思いを募らせてきました。
そして茨城大学の学生となり、伊藤ゼミで卒業研究として取り組んだのが、東日本大震災の被災体験の若い「語り部」の方たちへのインタビュー調査。宮城県の仙台市、石巻市、気仙沼市といった被災地に赴き、自身と同じ世代ながら語り部として活動している人たちに会い、話を聞いていきました。
「語り部のみなさんは、被災をしていない人たちに被災の経験の話を聞いてもらうことで、語っている自分自身の気持ちの整理ができるのだという話をしていて、それが印象に残っています」と佐藤さん。「だから、被災体験のない私にも、話を『聞く』という役割を担えるのではないかと考えることができました」。
今回のワークショップもまさにその思いで企画したものでした。
すなわち、台風19号の被災を経験していない茨城大学の大学生、留学生たちが、大子町に住む人たちからいかに体験や想いを「聞く」か――佐藤さんは、「すぐに話せる人もいれば、話せない人もいるけれど、誰しもが心の中に語りたいこと、物語があると思うんです。それを引き出し、語ってもらう機会を作れればと思いました」と語ります。模造紙や付箋を使った語りの可視化の仕掛けも、「どうしたら高校生たちと語りを共有できるか」と考え、工夫を凝らしたものです。
ワークショップを終えて、高校生たちの話を直に聞きながら、手応えも感じられたという佐藤さん。「高校生たちは最初は戸惑っていても、一個書きだすとそこからはポンポンとアイデアが出てくる。ひとりひとり、自分の中にアイデアがあるんだなと驚きました」と振り返りました。
 最後に記念撮影 前列中央でピースサインを見せているのが佐藤さん
最後に記念撮影 前列中央でピースサインを見せているのが佐藤さん
東日本大震災から12年。台風19号災害からは3年半が経とうとしています。大きな気象災害も頻発し、それぞれの地域で人びとはさまざまなリスクと向き合いつつ、懸命に生きています。その中で、多様な人たちが「語る」「聞く」という関係が生まれるどう作り、豊かなものにしてつないでいくか。大学生や高校生といった若い世代も、それぞれのバトンを手にし、前へ進もうとしています。
(取材・構成:茨城大学広報室 ※一部写真は大子町及び髙瀨一仁さんよりご提供いただきました)